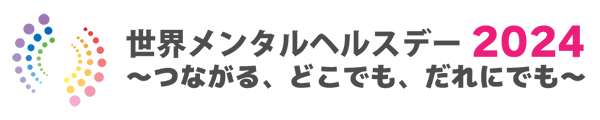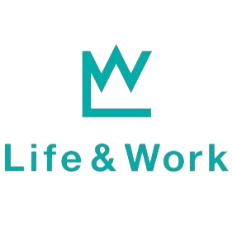11月は「過労死等防止啓発月間」

厚生労働省は「STOP!過労死」を掲げて、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」に定めており、事業主に対しても働き過ぎや長時間労働の削減に取り組む指導を行っています。2022年6月に発表された令和3年度「過労死等の労災補償状況」、特に精神障害の状況からポイントはどのようなところにあるのか、見ていきましょう。
ポイントは「ハラスメントの増加」
厚生労働省は過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを、平成14年以降年1回、取りまとめています。
令和3年度調査のポイントは、以下の通りです。
・脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況は請求件数、支給決定件数ともに減少
・精神障害に関する事案の請求件数は2,346件で前年度から295件増加し過去最多
・支給決定件数も629件で前年度から21件増加し過去最多
令和3年度「過労死等の労災補償状況」
精神障害の労災支給決定件数に関して出来事別にみてみると、パワーハラスメントに関する事案が125件で過去最多となっています。また、「同僚等からの暴行・いじめ・いやがらせ」に関する事案も61件、セクシャル・ハラスメントに関する事案が60件と、ハラスメントの事案は非常に多く認定されていることがわかります。
|
上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃などのパワーハラスメントを受けた |
125件 |
|
仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった |
71件 |
|
悲惨な事故や災害の体験、目撃をした |
66件 |
|
同僚等から、暴行または(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた |
61件 |
|
セクシャル・ハラスメントを受けた |
60件 |
ハラスメント対策は企業にとって必須事項に
このように、精神障害に関する労災はハラスメントの影響を受けて増加していることがうかがえます。ハラスメントに対する社会的な関心の高まりを背景として、今までは見過ごされてきた加害が取り上げられるようになりました。
そんな中、令和2年6月に改正労働施策総合推進法(通称パワハラ防止法)が大企業において義務化されるとともに、労災認定基準の出来事の類型に「パワーハラスメント」が追加されることになりました。さらに、令和4年4月からは中小企業を含むすべての事業者に施行されています。各企業はパワハラを防止するためにさまざまな措置をとることが義務づけられましたが、それでもパワハラによる被害は防止できていない状況です。
ハラスメントの問題は加害者の側にその意識が薄いことが特徴としてあります。防止のためには、どのようなことがハラスメントに該当するのかをきちんと理解したうえで、対策を講じていくことが不可欠です。防止対策を講じることで、損失を防ぐだけでなく、心理的安全性、会社への信頼感や働きやすさ、生産性の向上にもつながっていきます。
MRCでは、ハラスメントに関する対応方法や研修のご相談も受け付けていますので、ご気軽にご相談ください。